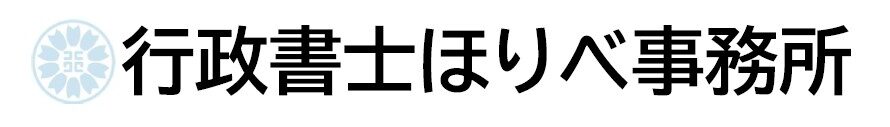建設業許可について その2
いつもたいへんお世話になっております。
今回は建設業法における、請負金額による許可の要否について書いていきます。建設業法では同法第2条で許可を受けて建設業を営む者を建設業者と定義していますが、許可を取らなければ一切建設業を営んではいけない、というわけではありません。
許可の要否
前回、建設業の29種類の工事を営む場合は、許可を取得することが求められると説明をしました。しかし、建設業法第3条ただし書では「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と、許可を受けることを要しない事業者を規定しています。政令で定める軽微な建設工事の条件は下の表のようになります。
| 建築一式工事(①、②いずれかに該当する場合) | ①1件の請負代金が1,500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事 |
「高額な工事を受注することはないから、許可の取得は考えなくていいかな」というのも一つの考え方です。許可取得には労力も伴います。しかし、昨今の建設業界においては元請け業者さまから許可の取得を求められることも増加しております。そして、事業を開始するにあたっては、軽微な工事に該当する場合であっても登録が必要な工種もあります。例としては、電気工事業などが挙げられます。工事の金額だけではなく、工種についてもしっかりと把握する必要があります。
許可の取得だけにとどまらず、コンプライアンスの向上が業界全体として求められています。ほりべ事務所ではどの種類、区分の建設業許可をとるのかといったところからもご相談を承っております。ご検討の際はお気軽のご連絡ください。