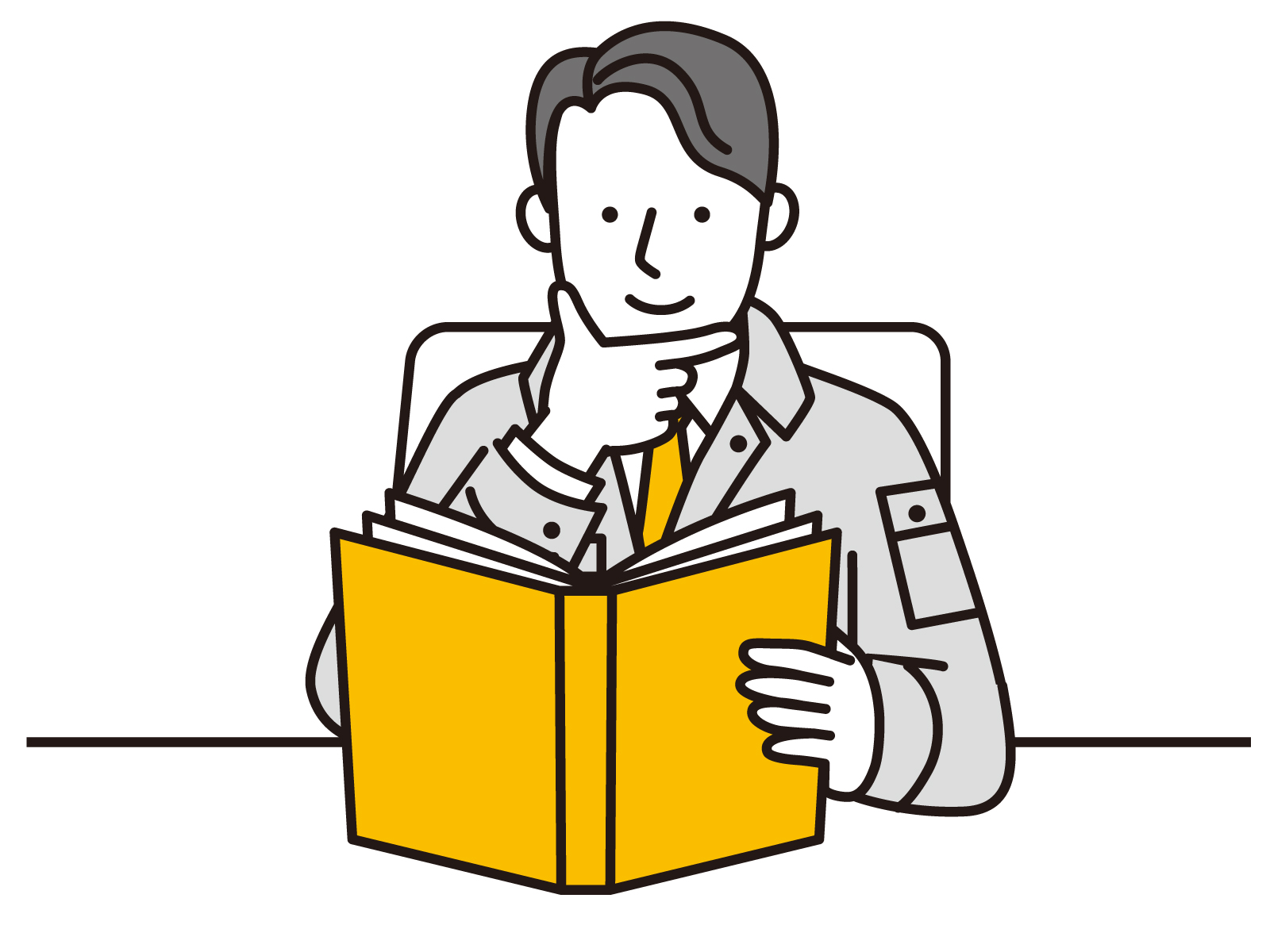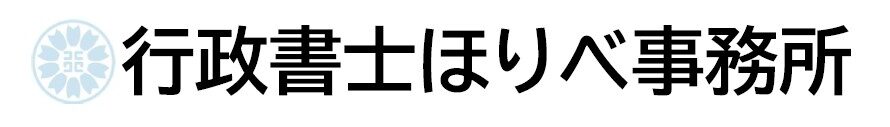建設業許可とは
建設業法では下記の軽微な工事を行うにあたって建設業の許可が不要とされています。
- 建築工事では1件の請負代金(消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築以外の工事では1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可を取得することにより、軽微な工事以外の工事まで受注することが可能になるとともに、お施主様からの信頼度も高まります。

建設業許可の種類と区分
建設業の許可の種類は営業所の所在によって「知事許可」と「大臣許可」に分けられます。
- 知事許可 特定の都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合。
- 大臣許可 複数の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合。
さらに種類とは異なる区分として「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
- 一般建設業
発注者から直接受注した工事につき元請からの下請け工事の請負金額が4,500万円未満(建築一式工事については7,000万円未満)である、または下請事業者としてだけ営業しようとする場合 - 特定建設業
発注者から直接受注した工事につき元請からの下請け工事の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)となる元請事業者
このように種類と区分により取得するべき許可は異なります。

5つの要件
許可を取得するにあたってはどのような体制で営業しているかが重要とされます。主に5つの要件について必要書類の作成、提出が求められます。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- 専任技術者を営業所においていること
- 請負契約に関して誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 結核要件に該当しないこと

許可取得のあと
許可を取得してからも行政に対する書類の提出は続きます。
- 終了届
毎事業年度の工事経歴や直前3年の工事施工金額、決算書類等を提出します。 - 許可の更新
建設業許可は5年間ごとなので許可取得から5年経過前に更新の申請を行います。
取得後も定期的に書類を提出し許可を受け続けられるようにします。事業の状況によっては業種の追加申請や産業廃棄物許可の取得も考えられます。さらに経営審査事項、入札参加申請を経て公共事業を直接請け負えることを検討することもあります。